|
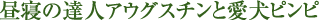 |
|
朝の爽やかな光が、開け放たれたベランダから仕事場に射し込む。
「ランララン、コモテキエロー」
酔っ払いのアウグスチンの、大きな歌声が階下を通り過ぎていく。歌は昔の曲、パッソドブレが多いのだが、同じ歌が何日も続いたり、ある日突然新しくなったりと、気ままに歌っている。隣のマリーおばさんに歌の内容について聞いてみたら、苦笑いしながら教えてくれた。
「アウグスチンは詩人だからね、自分で歌詞を作るから、日によって違うのよ」
まだ眠たげな村を揺り起こして、目を覚まして廻っているような、アウグスチンの歌声。しっかりとした発声と自信に満ちた節回しは、村の一日の始まりでもある。
彼は毎朝七時には隣村メシニージャの居酒屋アルヒーベにいる。こんなに朝早くから居酒屋が開店するのは、飲兵衛の多い左官屋たちの仕事が、朝八時に始まるからだ。ブランディ入りのカフェ、カラヒージョや、ブランディに甘口のアニス酒を混ぜたソル・イ・ソンブラを飲む。ソルとは太陽、ソンブラとは日蔭、琥珀色のブランディと透明なアニス酒を一緒にすることから、この名前がついた。でも、蒸留酒どうしだから、かなり強い一杯である。これを何杯か飲んで、体を温めてでかける剛の者もいる。アウグスチンはビール党で、朝から晩までビールしか飲まない。太陽がしっかり東の空に収まるころ、アウグスチンはフェレイローラ村に戻り、気がむくと、歌いながら村を廻るのだ。
「パンパララン、オレはとっくにあの世ゆき…、パンパパーン」
ときどき厭世的な歌詞が飛びだしてくるところがよい。アウグスチンは、六十歳を過ぎて、いまだ独身。白髪を短く刈りあげ、中肉中背のどちらかというといい男。いつも超若作りなシャツやパンツを身につけているが、彼のファンの若い外国人たちの差し入れである。太陽が天に昇りつめるまでは、広場の教会前の石段に座っているか、借りている畑を耕しているかのどちらかだ。生活は、村人からの手間仕事で賄っている。オレも家を工事していたときは、資材をネコ車で運んでもらった。冬になれば、いつも暖炉の薪運びを手伝ってもらう。まったく自由奔放、きままな生き方で、天衣無縫な男と呼びたくなる。
村に住み始めて一番驚いたのは、彼の存在そのものだった。アウグスチンには、いつも可愛い相棒がいる。小柄な犬で茶毛に白いブチがお腹にある表情豊かなピンピネーロ<愛称ピンピ>である。このコンビで、どこにでも変幻自在に現れる。
昼下がり、だれもいない広場の教会前の石段にアウグスチンが座っていた。今日はだいぶ飲んだらしく、赤ら顔をしている。彼の脇には、猫のように丸くなったピンピが寝ていた。広場を囲む四本のアカシアが、初夏の淡い風に揺られてサワサワと音を奏でている。
「いい風だね…、ここの日蔭は最高だ」
「イシー、ここは教会の門前だよ。最高に決まっているよ!」
いつものように、笑みを浮かべながらまぜかえしてきた。なんだか彼とおしゃべりしたくなり、隣に座らせてもらった。冷たい石段が心地よい。
「いまのうちに、薪を家のなかに運んでおこうかな…」
「ああ、オマエは暖炉好きだからなあ、冬、いつも煙突から煙がみえてるよ。近いうちに、庭の薪を運んでおいてやるよ」
赤い顔はしているものの、午前中の酔いはとりあえず醒めているらしく、受け答えはしっかりしていた。
「アウグスチンは、この村で生まれたんだよね?」
「そのとおりだ。ポルトゴス村のお産婆さんがとりあげてくれたらしい」
「生まれてからずっと、フェレイローラ村にいるわけだ」
「まあね、でも若いときにはお決まりの出稼ぎってやつで、ドイツに行ったり、バスク地方のパンプローナに行ったりしたことはあった」
「村の他の人たちと同じだね。それからは、この村に」
「そうだ。でもなんで、そんなこと訊くんだ?」
「だって、アウグスチンはこの村の守護神のように、ズーッとここにいるみたいだからさ!」
「確かにね。オレだってたまには旅に出たくなるときもあるよ。でもね、こんど旅立つときは、神様がお召しになるときさ」
酔えば陽気に、素面ならシリアスに、飲み過ぎれば、ところかまわず昼寝をする日々。
彼の家は、路地を挟んで向かいの左隣。外壁は村でもめずらしい、昔のままの石積みに、石灰を塗っただけのもの。玄関の扉は、覗き窓つきで、一応鉄格子で守られてはいるものの、ガラスは入っていない。夜になると、奥のほうからロウソクの灯りが漏れる。彼の家には、電気とガスがない。水道はあるが、もともと水の豊富な村だから、最近まで使い放題でタダ同然だった。さすがに何年か前、各戸に水道メーターがつき、料金を徴収するようになったが、彼にお金を払わせるなんて、まあ、この村ではありえない。煮炊きは、昔から村人がしていたように、暖炉を使う。まったく、キャンプ感覚の生活ではないか。
真夏の朝、村人の集まる広場でひと悶着あった。恒例の狂犬病予防接種の日だった。どの飼い主も、当然ながら獣医に接種料を払い、犬に予防注射してもらう。ところが、アウグスチンが接種に異議を申したてたのだ。
「ピンピは狂犬病じゃないから、注射は必要ないよ」
これには広場にいた村人も困ってしまった。マリーおばさんとは反対側の隣に住んでいる、ファティマおばさんが、諭すように云った。
「狂犬病じゃないから、ならないように注射するのが、予防接種なんだよ」
長老役カルロスがみかねて、助太刀を申しでた。彼が接種料二千ペセタを払えないのを知っているからだ。
「ピンピに三百ペセタ!」
百ペセタの金銅色のコインを三つ、獣医の大きなカバンの上にのせた。そこに居合わせた皆が同じようにコインを置き、必要な二千ペセタは即座に集まった。
「納得いかないよ。なんで、ピンピが注射されなきゃいけないんだ…」
彼の言葉に獣医も苦笑しながら、ピンピに予防接種した。アウグスチンは皆に礼をいうでもなく、ピンピを連れて居酒屋アルヒーベに行ってしまった。カウンター越しに理不尽な文句を云い、エドワルド親爺がなだめる様子が、絵を描いたように想像できる。
つぎの日、彼の家の扉にビニール袋がぶらさがっていた。マリーおばさんが作った蜂蜜漬けの揚げパン、ブニエロが入っているはずである。オレにも同じものを、おすそ分けしてくれたからだ。彼にとっては充分、気分直しになったことだろう。
さて、スペインといえば昼寝。これぬきに生活習慣は語れない。というか、スペイン人の生きる意味さえ左右しかねない、重要な理なのである。この昼寝の真実を教えてくれたのが、アウグスチンだった。
昼寝といえば、子供のころ、お腹にバスタオルをかけられ、いやいや寝かされたことを思いだす。それでもいつのまにか寝入っており、起こされると、おめざに紙に包まれたカリントウやオコシを渡される。そのときの嬉しさと、甘味の記憶がいまでも鮮明に甦る。そのとき以来昼寝はスペインにくるまで、完全に消失していた。ところが、南スペインに住み始めると、昼寝がいかに大事かがわかってきた。
まず、夏の日中の暑さが半端でない。大気が乾燥していることもあって、気温は摂氏五十度近くにまで上がる。反対に、日が沈み夜になれば、こんどは摂氏十五度くらいに下がる。南スペインは、気温の日較差が激しい風土だ。となれば当然、夏の活動は、涼しい午前中か、夕方以降になる。特にアンダルシア地方の夜は長いというか宵っ張りだから、生気を蓄えておかないと、村人との付き合いもままならない。
スペインでは、いまだ午後二時から五時まで、お店だろうが会社であろうが公共施設であろうが、すべて閉まる。さすがに巨大スーパーや百貨店は例外的に営業しているが、この時間、客は極端に少ない。こうなると昼寝の習慣は、ただ気候風土だけでは説明がつかなくなる。三時間におよぶ休み時間が、はたして本当に昼食と昼寝にあてられているのかは定かでないが、時間の使い方としては、非効率このうえない。でも、この習慣が改まるという話は、いまだ聞いたことがない。云ってみれば、スペイン人の生き方にかかわる、こだわりとなのだろう。
このあたりの解釈を、独断と偏見で考えてみたい。
どうも、スペイン人は、昼寝を挟んで一日を二つに分け、最初の半分は生きるため、あとの半分は人生を楽しむためにと、考えているようだ。だからこそ、サマータイム制もなんの異議なく、受け入れられるのだろう。人生を楽しむ時間が、それだけ長くなるのだから。昼寝は、生きるための労働を忘れさせ、人生を謳歌するための序曲となるのである。現実は、昼寝のあとにも仕事があるのだが、どこまで効率的におこなわれているか…。
スペインに来たてのころ、さすがのオレも、昼間寝ることにはなかなか馴染まなかった。暑い盛りであろうが、その暑さを享受してドライブを楽しみ、スケッチをしたりと、結構面白がっていた。ところが、アンダルシアの生活習慣に合わせようとすると、さすがに体がついていかなかった。例えば、夏祭りの目玉、フラメンコ大会の開演は夜十二時過ぎだし、レストランや居酒屋がいちばんの盛りあがりをみせるのは夜の十時以降である。それに合わせているうちに、気がついたときは、スペイン人のようにしっかり昼寝をとるようになっていた。
享楽的ともいえる生き方には、意外とすんなり体も精神も順応するものだ。いまでは変な罪悪感は消え、昼寝がどんなに心地よい夢を運んでくれるか、納得している。
アウグスチンは、昼寝の名人である。いや、昼寝の概念をもうひとつ超えた、達人といってもよいだろう。彼の昼寝はベッドの上だけでない。どこでもちょっとした木蔭があれば、そこが昼寝の場になっている。これが、とても魅惑的で、ときどき真似をさせてもらう。さすがにどこでもという達人技には至らないが、庭の柿の木蔭などは最高である。まあ、アウグスチンは、たまには昼寝でなく、酔いつぶれて寝入っていることもあるが、こんなときは、ピンピもご主人様をほっといて、さっさと村に帰ってきてしまう。
昼下がり、オレのお気にいりの場所に行ったら、アウグスチンが悠然と昼寝をしていた。昔の村の共同麦踏み場跡だ。村の広場から、東に三百メートルほど行ったところに、鉄平石を敷きつめた、直径二十メートルにも満たない平らな、円形の場所がある。目印は大きなクリの木。眼下にトレベレス河を望み、谷風に乗ってくる水音が、静かに重く、涼気を振るわせている。山に囲まれた景色が、光の変化を微妙に映し、なんだか時間がみえるような、壮大な空間である。
彼の小さな畑がこの近くにあり、大体、野良仕事のあとには、クリの木陰で昼寝をしているのだ。ベッドの上より、何十倍も気持ちのよい場所であることは確かだ。近づくと、アウグスチンの脇で寝ていたピンピがすぐに起きあがり、いつものように挨拶がてらとびついてきた。ピンピがあまりにもワサワサ駈け廻ったせいで、アウグスチンが起きてしまった。顔色をうかがうと、酔ってはいないようである。
「これ、ピンピ! オマエの恋人はオレだぞ。イシーにあまりイチャイチャするな、コラコラ、わかってるのかよ」
いつもの口癖が始まった。ピンピはどうもオレと気が合うらしく、特別仲がよい。実は、オレの家には高級ドッグフードが隠してあり、ついてくればいつもあげてはいるが、犬はそんなことだけで仲間意識は持ってくれるものではないと信じている。ピンピはとても賢く、酔っ払いのご主人様であろうと、アウグスチンをことのほか慕っていることはその表情や態度でよくみてとれる。
「ピンピ、オレとのことは、ヒ・ミ・ツ。いつも遊びに来てるもんな」
「なんだいそりゃ、浮気は人間だけがするもんだぞ。いやあ、よく寝たよ。ひさしぶりの畑仕事で、腰が痛い」
「オレたち、もう無理する歳じゃないよ。
「でもな、野菜くらいは自分で作らないと…、レタスはいるかい?」
「ありがとう、いつでもいただくよ。このあいだ、畑を覗かせてもらったけど、いろいろ作っているんだね」
「ジョルジオに頼まれて、泊り客用のジャガイモやトマトを栽培していることもあるんだけどね」
イタリア人のジョルジオと、デンマーク人のマルガレーテのふたりで旅籠を営んでいることは前に話した。
クリの花があたり一面に落ちて薄緑色に大地を染めている。頭上でミツバチや、真っ黒いお尻のクマンバチまでが、ブンブン飛び交っている。初夏の自然の大合唱である。
「オレの子供のころはな、ここでラバを使って小麦の脱穀をしたものさ。いまはただの見晴台でしかないが…。そう、いまごろだったよ、村人が皆集まってラバの尻を叩きながら脱穀したんだ。賑やかなもんだった。ほんのちょっと前の話だぜ」
「昔の麦踏み場がどうだったか、残念ながらわからないけど、ここは風が通って気持ちがいいね。それに、いつだったか、樫の木のあいだを狐がすり抜けるように歩いているのをみたし、向かいの山を、野生の山羊の群れが走り去るのもみたよ。ここでは、いつもなにか発見するんだ」
「そうだよな。同じ景色をみていても、そこには同じ情景はないということか。オレにとっての麦踏み場は、それこそ村人が集って、脱穀作業をする賑やかな場所だけど、オマエにはそれがみえないもんな」
なんだか、アウグスチンは寂しそうだった。昼寝のあいだ、彼はその昔の麦踏み場の世界で遊んでいたのかもしれない。
谷風が急にないできた。黄金色の光の矢が、谷あいに沿って深く射し込んでくる。もうじき、ゴツゴツとせりだした岩が茜色に染まりだす。オレがここで昼寝をしたら、どんな夢をみるのだろうか。まだ、達人の域にはおよばないとしても、栗の大木が、なにかを教えてくれるかな? こんどは、オレがここで昼寝をする番なのかもしれない。
秋のある日、アウグスチンが元気よく玄関のノッカーを叩いた。
「イシー、シャンピニオンは好きかい?」
みると、大きな籐カゴ一杯に、黄褐色の天然モノが入っていた。
「大好きだけど、どこにこんなにたくさん生えてるの?」
「ウーン、それは秘密だな。でも、そんなに好きなら、いくらでもとってきてやるよ」
こんな嬉しい差し入れをしてくれるのがアウグスチン。その夜は、迷わずシャンピニオンを使ったパスタにした。天然モノは香りが強く、良質のオリーブオイルにぴったり合う。たっぷりのニンニク、唐辛子、そして初夏に野原で摘んで乾燥させておいたオレガノを加え、塩・胡椒し、アルデンテに茹でたフェテチーネにからめて食べる。アルプハーラ地方の自然からの、秋の贈り物である。
アウグスチンの生活ぶりをみる限り、経済的には豊かとはいえない。というか、一般的解釈をすれば極貧といってよいだろう。しかし、村人に喜びを与え、皆から愛される生き方は、幸福者の証といえる。そして、そんな人柄を受け入れ、お互いの価値観を認めあう集落こそ、異邦人たちを受けいれる、真の村社会といえないだろうか。 |
|
|